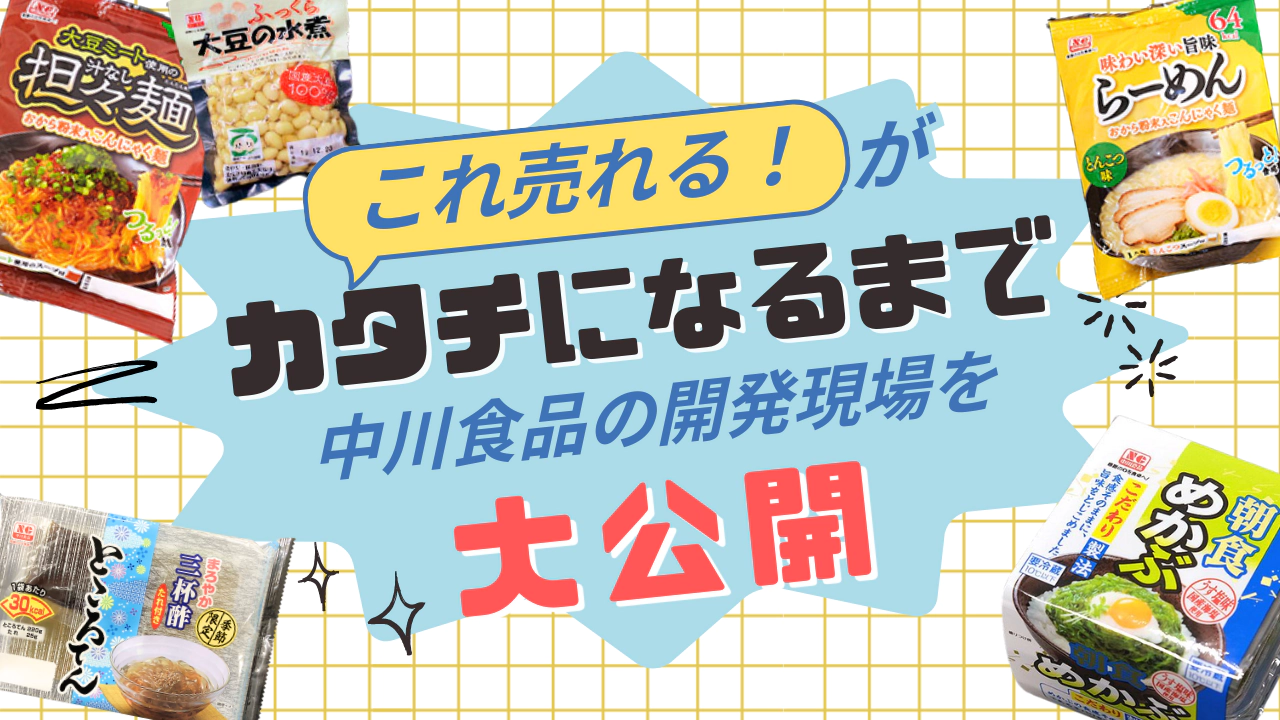



こんにゃくやところてん、めかぶ、そしてレトルト食品など、私たちの食卓でおなじみの商品を手がける中川食品株式会社。九州ではトップクラスのシェアを誇り、約60年の歴史をもちながら、今もなおチャレンジを続けています。この記事では、中川食品が大切にしている“新しい価値”とは何か。その中身をじっくりお届けします。
中川食品のスタートは、1965年。北九州市で創業者・中川博昭氏が立ち上げた、小さなこんにゃく工場でした。そこからコツコツと事業を広げ、こんにゃくにとどまらず、ところてん、めかぶ、レトルト食品といった商品まで手がけるようになりました。いまでは九州を中心に、沖縄・関西・関東まで流通網を持ち、特にこんにゃくにおいては九州で1〜2を争う企業として知られるようになったのです。
でも中川食品のすごさは、「守り」だけでなく「攻め」の姿勢にもあります。たとえば、季節に合わせた刺身こんにゃくや鍋用こんにゃく、健康志向を意識した海藻類の商品開発、さらにコンビニ向けの販路開拓など。時代のニーズを柔軟にとらえ、固定観念にとらわれず“新しい価値”を提案し続けているのです。
これは、60年の歴史とともに築き上げた製造技術や地元との信頼関係があるからこそできること。伝統と革新をバランスよく融合させながら、新しい食文化を切り拓いている——それが中川食品の強みです。
中川食品には、製造・営業・物流・商品管理・総務などの部署があります。一見するとそれぞれバラバラの仕事をしているようですが、実はこの5つが密に連携することで、“新しい価値”が生まれています。
たとえば、製造部は安定的で高品質な商品をつくるプロ集団。長年の経験に最新の技術を組み合わせ、安全でおいしい商品を生産しています。そこに、消費者の声を届けるのが営業部の役割。営業担当者は取引先と直接やりとりしながら、商品づくりのヒントを現場に届けます。
物流部は、そうして生まれた商品を“必要なときに、必要な量を、正しく”届ける縁の下の力持ち。賞味期限や温度管理が厳しい食品を扱うなかで、日々、緻密なオペレーションを実行しています。そして商品管理部は、商品の品質管理やパッケージ開発を担い、見た目も中身もブラッシュアップ。最後に、総務部が経理・人事・教育など、全体の基盤を支える。
こうして各部署が専門性を発揮しながらも協力し合うことで、中川食品は部署の垣根を越えて“新たな価値”を形にしています。
中川食品の企業理念は、「感謝の心を食卓へ」。この言葉には、創業当初から続く“想い”が込められています。食品メーカーとして、人々の健康や生活に直結する商品を扱う責任。その重みを社員一人ひとりが感じながら、日々の仕事に向き合っているのです。
たとえば、製造現場のスタッフは、毎日同じように見える作業にも、細やかな気配りと妥協のない姿勢で取り組んでいます。「この商品を手に取った人が、“おいしい”、“買ってよかった”と思ってくれるように」という気持ちが、商品のひとつひとつに込められているのです。
営業スタッフも同じ。スーパーのバイヤーと話すときも、「どう並べたらより多くのお客様に手に取ってもらえるか」「どんな売り場演出なら商品の魅力が伝わるか」といった視点で真剣に考え、提案しています。ただ商品を並べるだけではなく、“食卓に笑顔を届ける”という使命感をもって、日々の業務に取り組んでいるのです。
このように、「感謝の心を食卓へ」という理念は、全社員にとっての大切な道しるべ。その言葉が、働く人の姿勢に表れ、最終的には消費者の満足や信頼へとつながっていく——中川食品の“新たな価値”は、こうした想いから生まれているのです。
食品メーカーの営業と聞いて、ただ商品をお店に卸すだけと思われるかもしれません。でも中川食品の営業部は、その枠にとらわれず、もっと踏み込んだ価値づくりに挑戦しています。スーパーのバイヤーと一緒に、売れる仕組み、伝わる売り場づくりを考える——それが営業担当者の大切な役割なんです。
たとえば、こんにゃくのように季節によって需要が大きく変わる商品では、春夏はさっぱり食べられる刺身こんにゃく、秋冬は鍋料理に合うカットタイプなど、シーズンごとの提案が欠かせません。営業は、そうした提案に合わせてパッケージを変えたり、棚のどの位置に置くと手に取ってもらいやすいかといった「売り方」の工夫も提案しています。
実際には、陳列棚の中でも“ゴールデンゾーン”と呼ばれる腰の高さ付近に商品を置けるかどうかで、売上が大きく変わることもあります。さらに、子ども目線の下段には大容量タイプ、大人目線の上段には高価格帯のアイテムを配置するなど、売り場戦略は実に細やか。こうした知識やノウハウをバイヤーと共有しながら、一緒に売れる売り場をつくっていく事でお店やバイヤーの信頼を築いてゆきます。
そして、提案は売り場にとどまりません。試食イベントや販促用POPの制作、SNS連動キャンペーンのアイデアなど、営業担当者が主体となって企画を進めることも珍しくありません。お客様に「ただ安いから買う」のではなく、「試してみたくなる」「家族に食べさせたい」と思ってもらえるような体験をつくる——それが営業の目指す“新たな価値”です。
商品をいかに魅力的に作り、売り場で工夫して展開したとしても、それが必要なタイミングでお店に届かなければ意味がありません。中川食品の物流部は、「必要なときに、必要な商品を、必要な量だけ」届けることを最優先にしています。その使命を果たすことが、食品メーカーとしての信頼を築く基盤でもあるのです。
特に食品は鮮度や消費期限、温度管理など多くの制約があるため、物流の重要性は非常に高いもの。たとえば年末年始やお盆、夏の行楽シーズンなど、需要が一気に高まる時期には、ほんの少しの判断ミスが在庫不足や過剰在庫を招いてしまうこともあります。
そのため物流部では、営業部や製造部と連携し、過去の販売データや店舗の傾向を分析しながら、ピーク時の出荷計画を綿密に組み立てています。また、配送ルートや出荷スケジュールの最適化にも力を入れており、ムダを省いた効率的な物流体制の構築にも取り組んでいます。
こうして裏側で支えてくれている物流部の存在があるからこそ、私たち消費者は「いつでも欲しいときに買える」という安心を得ることができるのです。華やかさはなくとも、企業の信頼を根本から支える——それが物流の“価値”です。
中川食品が目指す“新たな価値”を形にするうえで欠かせない存在が、商品管理部です。ここでは商品の品質管理だけでなく、新商品開発やパッケージデザインの工夫など、消費者が商品に出会う瞬間から食べるまでの体験すべてに関わる仕事が行われています。
たとえば、めかぶの製造工程で取り入れている“間接加熱・冷却方式”は、まさに技術革新の成果。従来は直接湯水に触れることで、ぬめり成分や栄養素が流出してしまっていたのですが、この方式では二重管を用いた間接的な加熱・冷却を行うことで、めかぶ本来の食感や栄養をしっかり守ることができるのです。
さらに、環境への配慮も忘れません。パッケージでは、過剰包装を避けて簡易フィルムに切り替えたり、プラスチックトレーをなくすことでゴミの削減に取り組んだりと、時代のニーズに合った工夫がなされています。デザイン面でも、売り場で目立つように斜めレイアウトを採用したり、縦置き・横置きどちらでも見栄えがするような工夫を凝らしています。
商品管理部が担うのは、単なる商品改善ではなく、「こんな商品を食卓に置きたい」と思わせるきっかけを作ること。トレンドに敏感に反応しながら、食に新しい驚きや楽しさをプラスしていく。それこそが、中川食品の“新たな価値”をリードする原動力となっているのです。
中川食品では、商品の品質や売り方だけでなく、「どうすれば地球にやさしい会社になれるか」という視点でも“新しい価値”づくりに取り組んでいます。環境問題に対する社会的な関心が高まる中で、食品メーカーにできることは何か。中川食品はその問いに、実践で答え続けています。
まず注目したいのは、太陽光発電の導入です。約2年前から本格的に取り組み始め、現在では工場で使う電力の約25%を太陽光でまかなっています。また、従来使っていた重油の代わりに天然ガスを導入することで、エネルギー源のクリーン化も進めており、今では全体の50%以上を天然ガスでカバーしています。
さらに、製造過程で出る生ゴミの処理方法にも工夫があります。1日に約500kg出る食品廃棄物を、専用の分解装置で翌朝にはほぼゼロにするという仕組みを導入。これにより、廃棄物の量を大幅に減らすことができ、地域の処理コストへの貢献にもつながっています。
こうした取り組みは、「CSR(企業の社会的責任)」という枠にとどまらず、「環境へのやさしさ」そのものを商品やブランドの価値に変えていくチャレンジでもあります。「この商品は、地球にもやさしい」と思ってもらえることが、消費者にとって選びやすさにつながる。中川食品は、そうした未来型の価値観を大切にしながら、食のあり方を見直しているのです。
これまでスーパーを中心に展開してきた中川食品が、さらなる“新たな価値”を生むために踏み出したのが、コンビニ市場への進出です。全国展開する大手コンビニチェーンの厳しい基準をクリアすることは簡単ではありませんでしたが、それでも「国産こんにゃく」の品質と安定供給体制を武器に、挑戦を続けてきました。
当時、コンビニのおでんの具材には、輸入品が多く使われており、国産に切り替えたくても対応できるメーカーが少ないという課題がありました。中川食品はそこに着目し、「安全・安心・高品質な国産こんにゃく」を提供できるパートナーとして、自社の強みをアピール。営業と製造が一体となって品質向上に取り組みながら、粘り強く交渉を重ね、ついには大手チェーンとの取引を実現させたのです。
この成功により、中川食品の商品がこれまで知られていなかった地域でも手に取ってもらえるようになり、ブランドの認知度は一気に高まりました。さらに、コンビニからの厳しい品質管理の要求に応えることで、社内全体の生産体制がより高精度・高効率なものへと進化。販路の拡大は、ただ売上を伸ばすだけでなく、会社全体の成長を後押しする原動力にもなったのです。
中川食品では、若手社員が積極的にアイデアを出し、活躍する場面が増えています。「気づき活動」と呼ばれる社内制度では、年に一度、若手を含めた社員が自身の業務改善や商品提案などについて発表する機会があり、全社員で意見交換を行います。
たとえば、「製造ラインのこの部分を少し変えるだけで、作業効率が大きく改善されるのでは」といった現場目線の提案から、「SNSでのキャンペーンで若年層への訴求を狙おう」といったマーケティング的なアイデアまで、多種多様な意見が飛び交います。ベテラン社員もその意見をしっかり受け止め、一緒に改善を進めていく体制が整っているのです。
市場の変化が激しい今、若い世代の柔軟な発想やデジタルスキルは、企業にとって欠かせない武器。中川食品はその価値をいち早く認め、若手の力を活かす組織づくりを進めています。こうした姿勢が、“新たな価値”を生み出すためのエネルギーとなっているのです。
中川食品では、近年女性社員の活躍が目立つようになってきました。かつては製造部門では男性が中心で、女性の正社員は少ない状況でしたが、今では女性リーダーが現場をまとめる姿も当たり前になっています。
これは、会社として“多様な働き方”を積極的に受け入れ、キャリア支援を強化してきた結果です。育児や介護といったライフイベントを経験しても、安心して長く働ける環境を整えることで、女性社員が力を発揮できるようになったのです。
女性リーダーが加わることで、現場に柔らかく繊細な視点が加わり、商品開発やパッケージデザインにも新しい感性が活かされています。たとえば「このサイズのパッケージは、手が小さい人にも持ちやすいのでは?」といった細やかなアイデアが、実際の改善につながることも少なくありません。
多様な人が活躍することで、組織の可能性はさらに広がっていきます。中川食品はこれからも性別や年齢に関係なく、誰もが挑戦できる会社を目指しているのです。
中川食品の“新たな価値”は、商品や社内だけにとどまりません。地域とのつながりを大切にし、地元に貢献する活動にも力を入れています。その一環が、地元の中高生や大学生を対象とした工場見学の受け入れです。
食品づくりの現場を実際に見てもらい、安心・安全へのこだわりや、ものづくりの面白さを伝えることで、将来の仕事選びや地域への関心を育てるきっかけにしています。また、地域イベントやフードフェスなどに出店し、自社商品を試食してもらう取り組みも積極的に行っています。
「こんにゃくってこんなにいろんな種類があるんだ」「めかぶって意外と美味しい!」といった新しい発見を通じて、地元の方々とつながりながら、健康や地産地消の価値観を広げていく。中川食品の取り組みは、地域と“共に育つ”ことを大切にした、温かい価値づくりでもあるのです。
中川食品が見据えるこれからのビジョン。それは、これまで積み重ねてきた技術や経験を活かしながら、さらに社会や環境と調和した“未来の食”をつくっていくことです。具体的には次のような展望があります。
このように、“ただ商品をつくって売る”のではなく、その先にある人々の暮らしや社会全体を豊かにすること。それが中川食品の考える“新たな価値”であり、未来への責任でもあるのです。
中川食品が挑戦し続けている“新たな価値”とは、一言でいえば「食を通して人と人、地域、地球がつながること」。60年という歴史のなかで、時代や社会の変化に柔軟に対応しながら、常に挑戦し、進化してきました。
伝統にとらわれず、若手の声や地域の声に耳を傾け、女性の視点や環境への配慮も取り入れながら、新しい商品やサービスを生み出す。その積み重ねが、消費者の「美味しい」「うれしい」という気持ちにつながり、さらにその先にある“笑顔の食卓”をつくっているのです。
「感謝の心を食卓へ」という理念のもと、中川食品はこれからも変わらずに、でも進化し続けながら、私たちの食の未来を支えていくはずです。食品メーカーの枠を越えて、暮らしや社会と共に歩む存在として、今後の展開に大いに期待したい企業です。